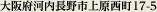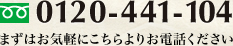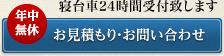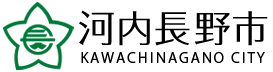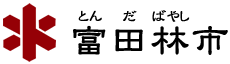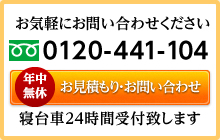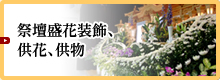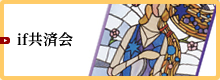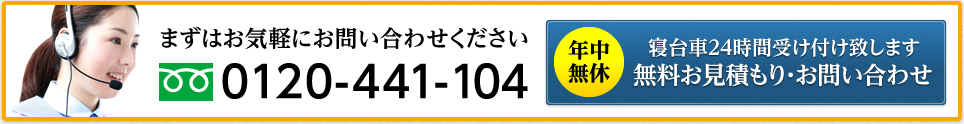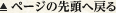「 相続された預貯金債権の過払い制度 」
この制度により、
一定の金額までは相続人が単独で
預貯金を引き出せるようになりました。
法定相続分の3分の1まで、
最大150万までとなります。
残りの3分の2を引き出すためには
やはり遺産分割の確定が必要となり、
故人の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、
遺産分割協議書などを添えて
金融機関での手続きを行います。
仮払いを受けた場合は、その金額分を
遺産分割の際に、
相続額から差し引かれます。
その他、
家庭裁判所の保全処分で
仮払いの必要性があると認められる場合、
他の共同相続人の利益を害さない限り、
家庭裁判所の判断で過払いが認められるようになりました。
引き出し額に上限はなく、
申立額の範囲以内で必要性が認められれば、
特定の預貯金の全部を所得することもできる点が
メリットですが、家庭裁判所への申立てなど
煩雑な手続きが必要になります。
預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類
遺言書が無い場合
( 銀行 )
・故人の戸籍謄本( 生まれてからの分 )
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押された銀行所定の用紙(相続届)
・遺産分割協議書
( 郵便局 )
・故人の戸籍謄本( 生まれてからの分 )
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・名義書換請求書等
・同意書または遺産分割協議書
遺言書がある場合
( 預貯金の引き出しや名義変更を行うのに必要な書類 )
・遺言書
・遺言者の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書
死亡後の銀行口座の手続き
① 取引銀行に連絡
② 必要書類の確認と取得
③ 口座凍結
④ 必要書類の準備
⑤ 遺産分割の提出
⑥ 必要書類の提出
⑦ 口座解約または名義変更
遺族サポート
河内長野市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-53-1111
富田林市役所 遺族サポート
( 代表 )0721-25-1000
大阪狭山市役所 遺族サポート
( 代表 )072-366-0011
その他手続きリスト
▶︎ 所得税の準確定申告
▶︎ 児童扶養手当について